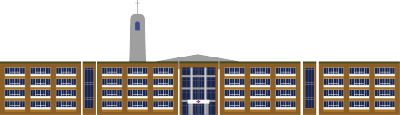-
入試
- 2025.10.14
 2026年度 高等学校入試試験範囲について
2026年度 高等学校入試試験範囲について
2026年度入試における各教科の試験範囲について公開いたします。
【 国 語 】
〔学特入試〕
現代文分野の大問(評論または実用的文章の問題、文学的文章または随筆の問題)を2題出題する。
〔一般入試〕
学特入試と同じ
<ポイント>
現代文分野では評論か実用的文章の問題と、文学的文章か随筆での問題、計2題が出題される。
評論や実用的文章の問題では、漢字の読み書きをはじめ、読解力の基礎を確かめるための指示語・接続詞・言い換えの表現などを問いながら、著者の主張に迫る設問へと続く。文学的文章か随筆の問題では、登場人物の言動や情景描写などから、登場人物の心理をつかむ設問や、その場面の主題に迫る設問へと続く。
合計100点のうち、漢字や語句の意味、文法などの知識を問う問題が約4割、文章の内容を読み取る問題が約6割の配分で出題される。総じて2025年度入試と同様の出題形式となっている。
【 数 学 】
学特入試、一般入試とも傾向は同じです。難易度に差はありません。
最初の計算問題は10題で40点分の配点となっています。
正負の数の計算、文字を含む四則演算、根号を含む式の展開、展開、因数分解、方程式(解の公式)、連立方程式などは毎年出題していますので落ち着いて解くようにして下さい。
2番以降は、「方程式」、「関数」、「図形」、「場合の数・確率」、「データの活用」、「総合問題」の分野から出題します。
ただし、中学3年生の後半に学習する「円の性質」、「三平方の定理」、「標本調査」は出題しません。
問題量が多いので解ける問題から解くように心掛けましょう。
最後に、入試では問題用紙に書いた解答と解答用紙に書いた解答が移し間違っていたり、解答欄を間違えたりしないように気を付けて下さい。
【 英 語 】
◇学業特別奨学生入試
英語科・普通科共通問題。一部、科別問題を含む。リスニングは共通問題。
<時間配分>
Listening → 約10分(放送は1回のみ)
Writing → 約40分
<配点>
Listening → 20%
Writing → 80%
<Writing問題形式>
( 共 通 ) ・文法問題 ・会話問題 ・長文問題1題
(別問題・普通科) ・整序(並べ替え)問題 ・長文の空所補充問題(新形式)
(別問題・ 英語科) ・短文の語句空所補充問題 ・英文整序問題(新形式)
◇一般入試
英語科・普通科共通問題。一部、科別問題を含む。リスニングは共通問題
<時間配分>
Listening → 約10分(放送は1回のみ)
Writing → 約40分
<配点>
Listening → 20%
Writing → 80%
<Writing問題形式>
( 共 通 ) ・文法問題 ・会話問題・長文問題1題
(別問題・普通科) ・語彙問題 ・要約穴埋め問題(新形式)
(別問題・ 英語科) ・語彙問題 ・要約穴埋め問題(新形式)
(注)10月1日現在の予定です。若干の変更の可能性もあります。
学特入試・一般入試ともに、科別問題で新形式の問題があります。
全般的には、中学校の学習内容に加えて、発展的内容も問われます。中学の教科書の基本的事項(単語・熟語・文法)はもちろんですが、応用力も身につけておいてください。長文問題では内容把握を中心に出題されます。時間内に解き終わるように、長文読解力もつけておきましょう。
【 理 科 】
実験や観察の問題が多く出題される。教科書に掲載された実験や観察はよく復習をしておくこと。
<物理分野>
音・光・力・電気に関する分野で、計算を必要とする問題も出題される。また、実験や観察から得た情報を読み取ったり、考えたりする問題も出題されるので、教科書にある実験や観察、その中で使用する機器の特徴、導き出された定理や法則をよく理解しておくこと。定理や法則の名前だけではなく、その内容まで充分に学習しておく。
<化学分野>
状態変化、化学変化、原子や分子、物質の性質に関する分野で、教科書にある実験や観察の操作や結果、注意点などを理解しておく。また、実験や観察でわかる物質の性質、教科書に載っている原子や分子の元素記号や化学式、そして、化学反応を表す化学反応式も書けるようにしておくこと。
<生物分野>
植物や動物やヒトのからだ、生物同士のつながりといった、いわゆる生命体に関する分野で、それぞれの動植物全体を大きくとらえての共通した特徴、異なる特徴を整理し、系統的に理解しておく。また、動植物の特徴ある部分のはたらきや、その必要性についても学習する。また、よく使われる観察や実験、試薬や溶液についても、充分に復習しておくこと。
<地学分野>
地学分野 地層・火山・地震、気象に関する問題で、最近話題になった事象や発生した現象についての問題が出題されることが多い。また計算問題が出題されることもある。
なお、天文分野については、中学校での教科指導の進捗を考慮して、学特・一般試験とも出題範囲から除外する。
全体的に、教科書を中心とし、単なる丸暗記ではなく、自分の言葉で説明できるよう準備することが必要である。
【 社 会 】
<地理>
・学業特別奨学生入試
世界地理は北アメリカ州より出題。地形や気候、その地域の特色をよくみておくこと。
日本地理は近畿地方より出題。地形や工業の特色をよくみておくこと。
・一般入試
世界地理は、冷帯や寒帯地域の気候について出題。この地域の文化や生活様式、雨温図などもよく見ておくこと。
日本地理は、九州地方の気候や地形、文化について出題。この地域の地形や生活文化、雨温図などもよく見ておくこと。
<歴史>
・学業特別奨学生入試
近畿地方にゆかりのある建造物(古代~近世)から関連して出題。また、昭和100年の節目の年でもあるので、昭和の内容も把握しておくこと。
・一般入試
江戸時代の範囲から出題。江戸幕府成立から明治維新までの流れ(17世紀初~19世紀後半)を把握しておくこと。特に政治、経済、文化でどのような動きがあったか、把握しておくこと。年表や教科書に載っているような資料(絵や地図)もよく見ておくこと。
<公民>
・学業特別奨学生入試
新しい人権分野から出題。人権の名称とその内容を把握しておくこと。
・一般入試
人権と日本国憲法から出題。憲法の成立とその特徴について把握しておくこと。